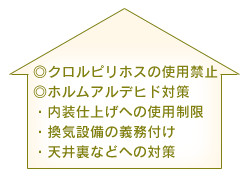◆概要
平成15年の建築基準法の改正で、シックハウス対策としてクロルピリホスの使用禁止、ホルムアルデヒドを含んだ内装材の使用制限、換気設備の設置義務付けがされました。
しかし建築基準法はあくまでも建築物の最低基準を定めたものであり、この法律を守るだけではシックハウス問題を解決することは決してできません。
【シックハウス対策に係る建築基準法の概要】
・規制対象とする化学物質
規制対象となる化学物質はクロルピリホス及びホルムアルデヒドです
・クロルピリホスに関する建築材料の規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用は全面禁止です
※クロルピリホスが添加された建築材料のうち、建築物の部分として5年以上使用したものは除外されます
・ホルムアルデヒドに関する建築材料及び換気設備の規制
■「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕上げ部分への使用面積の制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の使用面積が制限されます
○第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は、内装仕上げ材に使用してはならない
○第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(F☆☆)〜第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(F☆☆☆)については、一定の面積の制限があります
○規制対象外建築材料(F☆☆☆☆)については、使用面積の制限はありません
■換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、原則として全くの建築物で機械換気設備の設置を義務づけられています
■天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材(F☆☆☆以上)とするか機械換気設備を天井裏なども換気できる構造としなければなりません
※ホルムアルデヒドの発散量に応じて、JIS、JASによりF☆☆☆☆のように等級付けがされています。
◆クロルピリホス規制
※クロルピリホスはシロアリ駆除剤や農薬、殺虫剤などとして、幅広く使用されてきた有機リン系の化学物質です。建築基準法で一切の使用を禁止されている化学物質はクロルピリホスのみですが、その代替としてシロアリ駆除剤などに使用されている化学物質にも毒性の強いものが多くあり、それらの物質についての規制は現在のところありません。
【クロルピリホスの特徴・毒性】
○特徴
■常温の時は無色または白色の結晶
■有機リン系農薬成分
■分解しにくいため、環境残留性が心配される
■水に難溶、有機溶剤に易溶
■防虫加工(フローリングなど)、防蟻剤(土壌処理用)、シロアリ駆除剤、防腐剤などに使用される
■殺虫剤としては、リンゴやナシのアブラムシやハマキムシ、樹木のアメリカシロヒトリの駆除などに使用される
○毒性・症状など
■突然変異、神経毒性が強い劇物、魚毒性が強い
■肩こり、冷え、くしゃみ、激しいアレルギー症状、目の痛み、疲労感、狭窄感、肺水腫様状態、食欲不振、吐き気、下痢、瞳孔収縮、震えなどの症状を引き起こす
■急性毒性の場合は縮瞳、意識混濁、痙攣、肺水腫、呼吸困難などを起こす
■コリンエステラーゼという酵素の働きを阻害してアセチルコリンが分解されずに、興奮状態が続き、死に至る場合もある
クロルピリホスを塗布・散布した建材や、クロルピリホスを含有する建材などの使用は禁止されています。防蟻剤などの現場施工はもちろん、クロルピリホスを添加した建材の使用も全て禁止です。
ただし、クロルピリホスを添加した建材については、建築物に用いられた状態で5年以上経ったものは規制対象外となります。建築後5年以内に改築工事を行う際には、クロルピリホスを添加した建材は除去しなければなりません。